
ケアマネジャーの業務多忙すぎて終わらない。先輩が何も教えてくれない。
...ケアマネジャーを長くしていると「辞めたい」と思うことは何度もありました。
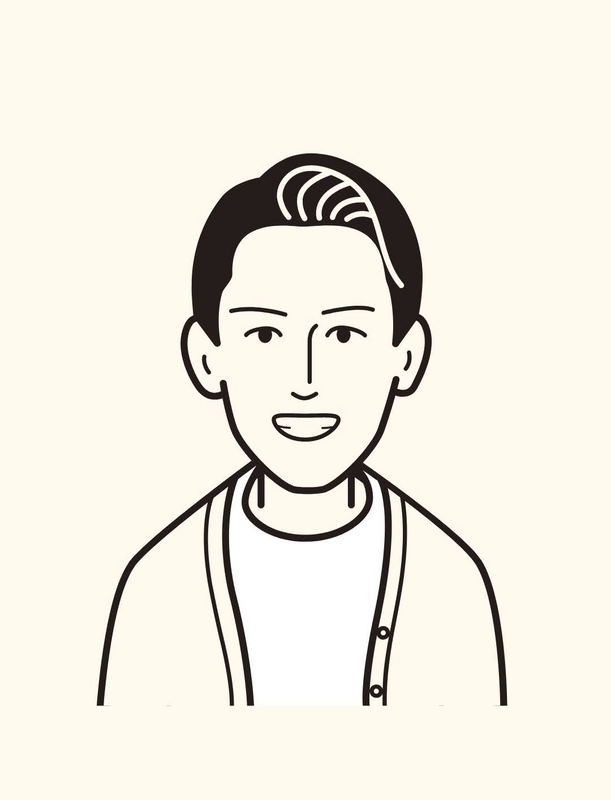
こんにちは、ケアマネジャー歴11年のまさたけ(@masa_take14)です。
当ブログでは、ケアマネジャーを始めたい方、始めたばかりの方向けのコンテンツを発信しております。
この記事では、ケアマネジャーの仕事が大変、辞めたいと感じたときのエピソードや、辞めたい時の乗り越え方についてを解説しています。
紹介する対処法を実践することで、ケアマネジャーの仕事が楽になるはず。
- 責任が重たすぎる。→課題の分離をしよう。
- やっても終わらない業務の多さに疲弊してる。→事業所と、業務分担する。
- 時間が足りない。→スケジュール・タスク管理術を身につける。
- 覚えることが多すぎる。→自分が覚えたことを記録して、自身をつけよう。
- 人間関係が大変。→続く人間関係、続かない人間関係とは?
- 辞めたくなる前に、対策を。
- 転職で気を付けたいポイントは?
責任が重たすぎる。→課題の分離をしよう。
「自分が提案したサービスで、利用者の生活が始まることに、責任を感じてしまう。」
新人の頃はその責任感に押しつぶされそうでした。同時にこんなプレッシャーにもビクともしない先輩ケアマネジャー凄いな、と。
この責任から解き放たれるためには、以下のような考え方が重要です。
- 介護サービスはケアマネジャーだけでは決めない。
- サービス事業所を信じる・頼る。
- 最初の決定が全てではない。
この3つを、もう少し深彫りしてお伝えします。
介護サービスは、ケアマネジャーだけで決めない・考えない。
ケアマネジメントプロセスでは、以下のような流れが一般的。
- 利用者から話(困ったこと)を聞くアセスメント。
- 困ったことに対する対策(介護サービス)を提案。
- 利用者が決定する。
- サービスを調整。(ケアプラン作成)
- モニタリング。
受ける介護サービスは、利用者が選択する。が基本です。
「利用者が決定する」ことで、すべて責任がケアマネジャーにある。という考え方は責任を背負い込み過ぎ。(まじめで優しい方は、このような考え方をしがち)
①利用者からの相談を受けて。
②ケアマネジャーは対策(介護サービスなど)を提案し。
③利用者が、受ける介護サービスが決める。
この過程(プロセス)を大切にしましょう。
サービス事業所を信じる・頼る。
サービス事業所にお願いしたものの、大変なケースだからといって心配しずぎるケアマネジャーがいます。(過去の私です)
サービス事業所は専門家。サービス事業所を信じ・頼っていきましょう。
サービス事業所は、その分野のプロなのでケアマネジャーより深い知識と経験があります。色々口出しをすると、ケアマネジャーとサービス事業所との信頼関係も崩れますし、ケアマネが口出しすると、本来なら上手くいくサービスも上手くいきません。
サービス開始時から、サービスの微調整が必要になるコトが前提。
最初に調整をしたサービスで、この先は安泰!という訳にはいきません。
ケアマネジャー始めたての頃は、最初の相談で、すべての悩みを汲み取ることができていないこともありサービス調整ばかりでした。(10年経ってもまだまだ...)
介護サービスが始まったばかりの時期は、サービスの微調整をすることの方が多いです。理由は、私の力不足はもちろんですが、利用者が「思ってたのと違う。」と感じるから。
”百聞は一見に如かず”で、利用者自身も、聞いてみるのと体験することでは、違った印象を持つことが多いです。
サービス開始して、数か月はサービスの微調整がでるだろう。と、心構えしておくと精神的にも、スケジュール的にも余裕が生まれます。
やっても終わらない業務の多さに疲弊してる。→事業所と、業務分担する。
ケアマネジャーの仕事は多岐に渡り、”ここまでが仕事”という線引きが無いのが辛いところ。
とりあえずケアマネジャーに!という流れに身を任せていると、仕事が終わりません。(そんな辛い過去もありました)
少しずつ業務分担すること。が大切です。
ケアマネジャーじゃなくても良いことは、他に適任がいる可能性が高いです。(仕事をお願いすることに罪を感じてはいけない)
利用者からサービスについての問い合わせやクレームがあったら、(可能な限り)直接サービス事業所へ問い合わせを確認をお願いする。
(サービス事業所からの利用者・家族への確認も同じです)
”餅は餅屋に。”その分野のことは、その専門家に直接聞いてもらった方がいいし、利用者としても相手の言い分や説明を聞くことで納得する事が多くあります。
ケアマネジャーは、そのように業務分担をすることも大切なことが大切な仕事です。
時間が足りない。→スケジュール・タスク管理術を身につける。
ケアマネジャーは、自分の時間管理が大切な職種。今まで現場で勤めていた方がほとんどなので、”時間管理”ができない。が当たりまえです。
なので、スケジュール管理術の勉強を行い、スケジュール帳や、スマホを使って”時間管理”を行う事が必要です。
覚えることが多すぎる。→自分が覚えたことを記録して、自身をつけよう。
現場に比べると、決まったスケジュールがなく幅広い仕事範囲をカバーするケアマネジャー。することが多く新人の頃は続けていけるか不安でした。
- ケアプランの作成。
- 支援経過記録。
- 役所への手続き。
- 介護保険以外への橋渡し。
- 給付管理。
など、ここに書き忘れているくらい多岐にわたります。
そこで実践してほしいのが、身につけた知識を貯めていくこと。
私はエクセルに覚えた事をジャンル毎に分けて整理しました。
これは、先輩方へ質問の回数が減り。自分が身につけた知識を振り返ることで、自己肯定感が上がります。
知識は貯めてて損はありません。
人間関係が大変。→続く人間関係、続かない人間関係とは?
ケアマネジャーの人間関係は
- 利用者・家族。
- 同じ事業所のケアマネジャー。
- 他事業所の方々。
大きく分けて、3つの人間関係があります。
人の悩みは人間関係から生まれます。
1、2はある程度、コントロールしやすいですが、3については転職をするほかありません。まずは管理者と合うか?が大切なポイントになります。
人数が少ない事業所は、管理者との関りが多いので合う・合わないは重要なポイントになります。
辞めたくなる前に、対策を。
覚悟を決めてケアマネジャーの仕事に就いたけど、大変に感じるのは仕方のないことです。
今まで行ってきた直接的な介護の仕事とは違い、間接的な仕事がほとんど。
初めてのことが多く、疲れます。なので、辞めたくなる気持ちがよく分かります。
ですが、対策することで景色がガラッと変わることもあります。
転職で気を付けたいポイントは?
24時間の生活を支えるケアマネジャーなので、ワークライフバランを大切にしているサービス事業所選びが大切です。
確認しとけ
— ケアマネ応援家┃歴11年 (@caremane_m) 2024年2月11日
ケアマネには5年に1度死に物狂いで受けなければいけない更新研修がある。その更新研修には「時間とお金」が必要。
研修期間を勤務として扱い、研修費用を出してくれる会社はケアマネの事を大切にしている証拠。
転職の際は要確認ですッ🤣👍
確認しとけ2
— ケアマネ応援家┃歴11年 (@caremane_m) 2024年2月11日
利用者の生活は24時間続いている。だから居宅ケアマネジャーは24時間電話がかかってくる可能性がある。
休日でも会社携帯を24時間持っておけ。という会社はブラック。
転職の際は電話当番制度がしっかりしている事業所か確認を。
ライフワークバランスは大切ッ🤣👍
確認しとけ3
— ケアマネ応援家┃歴11年 (@caremane_m) 2024年2月11日
初めてのケアマネで研修期間はあるのか?
新人教育に時間をかけない会社ではケアマネとして成長できない。なぜならケアマネは現場での経験はほぼ生かされないから。
3か月の教育期間がある事業所を選ぼうッ🤣👍
合格率が低い、狭き門を通り抜けたあなたなら、きっと大丈夫。ケアマネジャーの仕事は大変ですが、色々な方法を試しながら継続・成長していきましょう!
ではまた。







