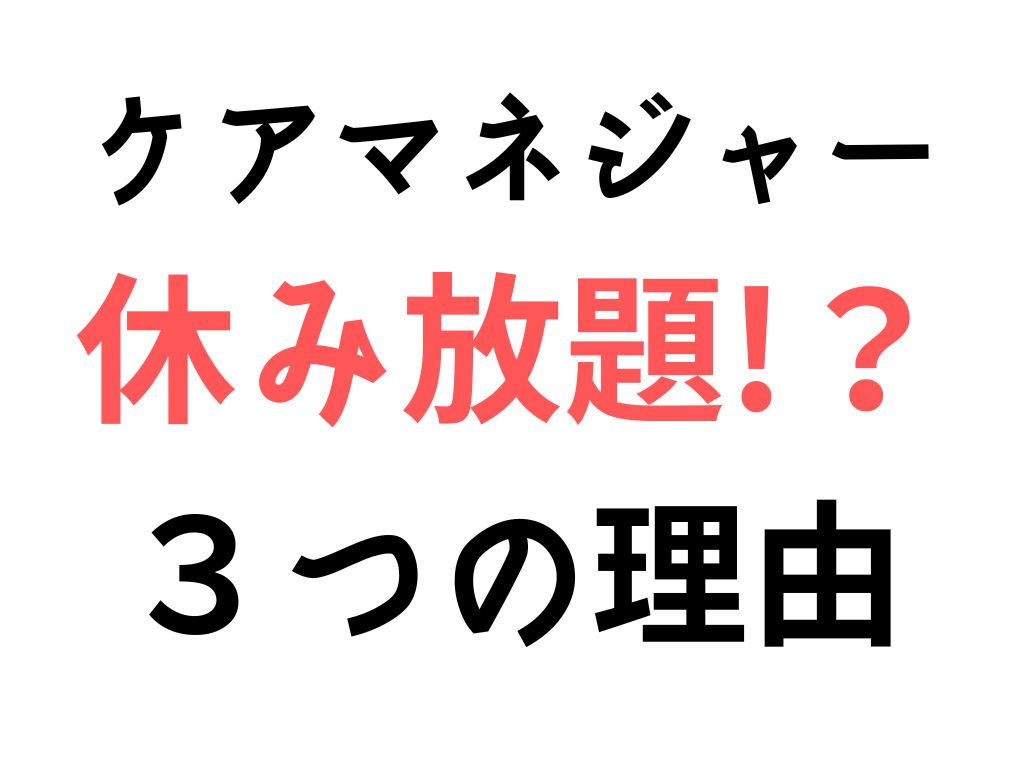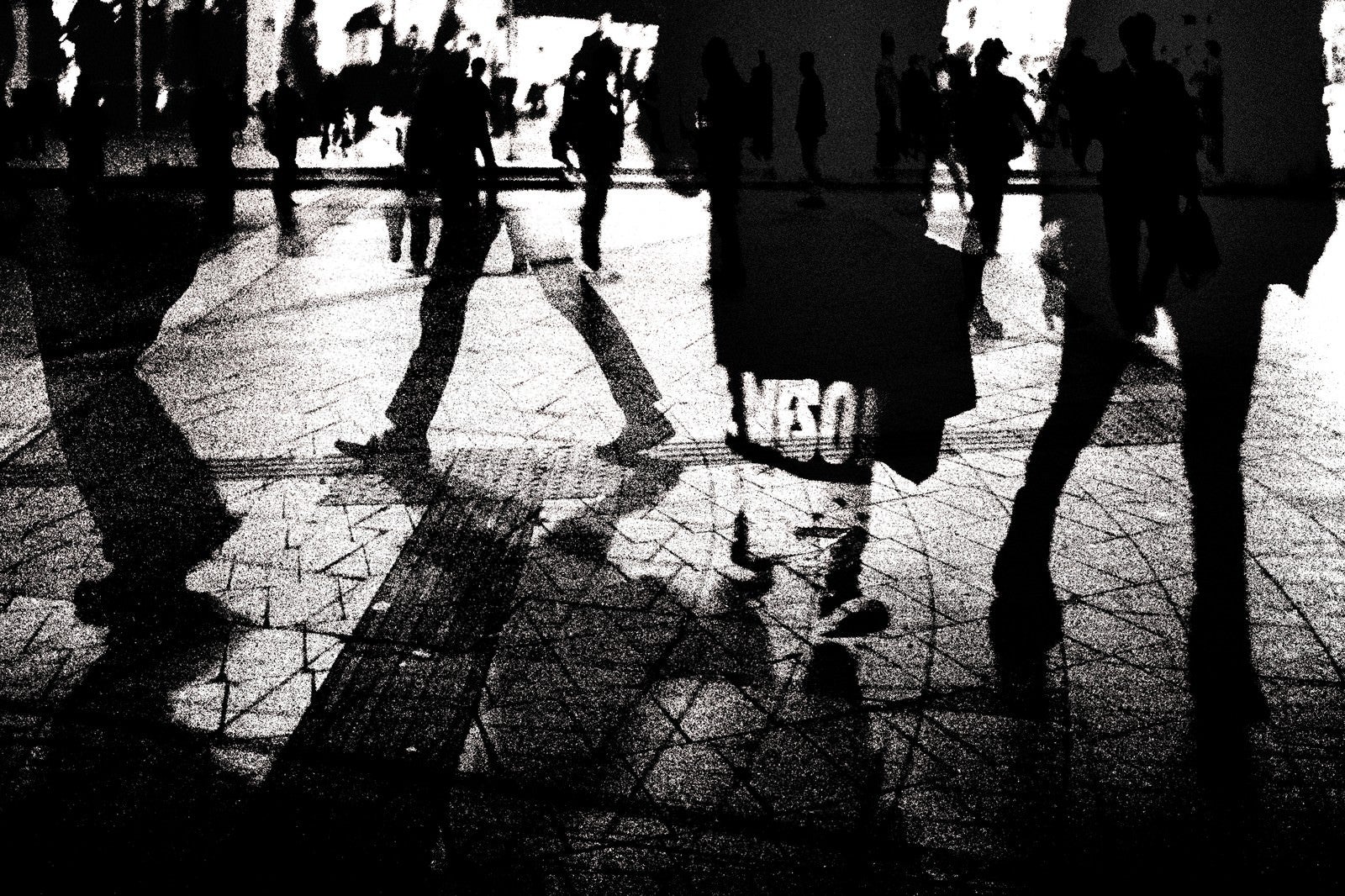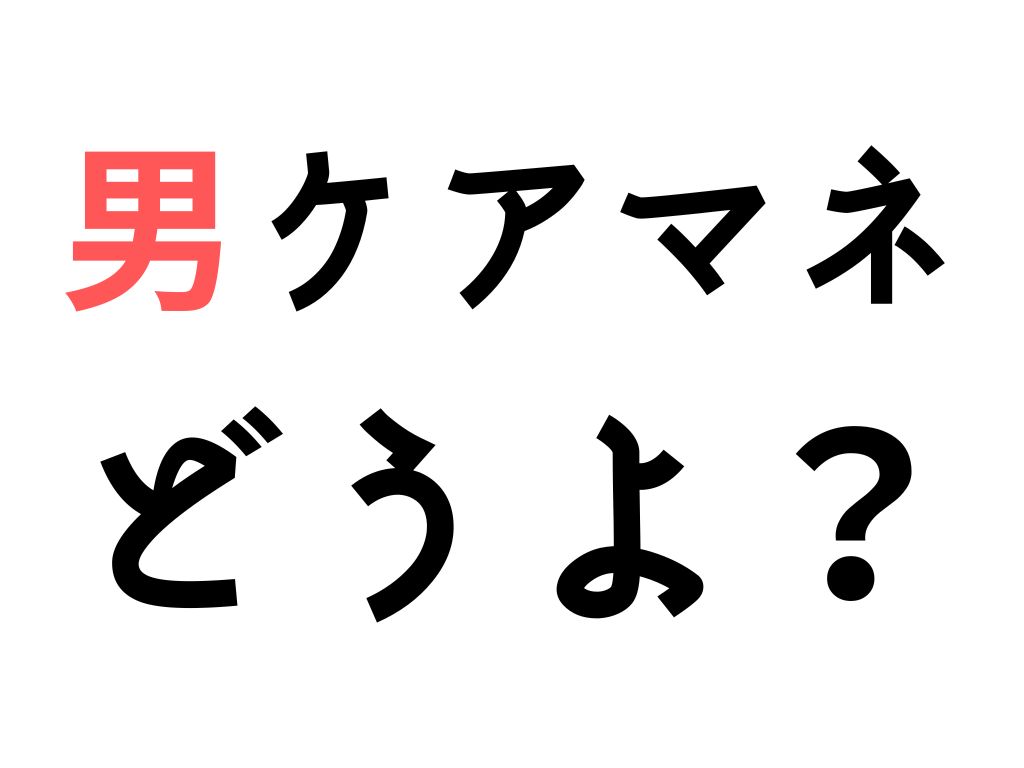
(更新日:2024.04.25)
これからケアマネジャーとして働く前は、
「一家の大黒柱としてケアマネジャーの給料でやっていけるのか?」
「男としてケアマネジャーとして働けるのか?」悩んでいました。
結果として、迷いながらもケアマネジャーへ転職して良かったと後悔はありません。
理由はケアマネジャーへ転職し、プライベートと仕事が両立でき、充実した毎日を送っているからです。
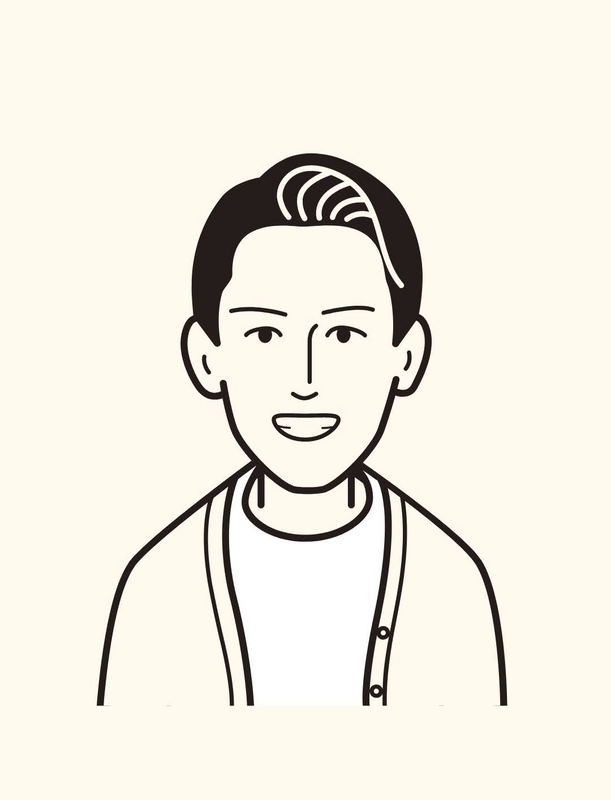
こんにちは、ケアマネジャー歴11年のまさたけ(@masa_take14)です。
当ブログでは、ケアマネジャーを始めたい方、始めたばかりの方向けのコンテンツを発信しております。
この記事では、アラフォー妻子持ちの筆者が、介護職からケアマネジャーに転職して良かったこと、そうでなかったエピソードをお伝えします。
ケアマネジャーへの転職を迷っている方の悩みが一つでも解決できれば幸いです。
- 男性ケアマネジャーには、こんな需要がある
- ケアマネジャー収入は??私は共働きしてます。
- 急な休みは、ケアマネジャーの方が対応しやすい
- 女性心を知らない男性ケアマネジャーは辛い
- 男だって、ケアマネジャーで人生を謳歌できる
男性ケアマネジャーには、こんな需要がある
男性ケアマネジャーは、意外と需要が高いです。
嘘!?男性ケアマネジャー不人気説。女性がニーズがありそうなケアマネですが、そうでもない。1人暮らしの男性、言葉がきつい女性利用者(本人に悪気はない場合も)、主介護者が息子、男性好きの女性利用者...。男性ケアマネジャーは割と需要があります。(歴10年が言うんだから間違いない)
— ケアマネ応援家|歴10年 (@caremane_m) May 1, 2023
男性ケアマネジャーは、女性ケアマネジャーとの相性が悪い利用者・家族への対応が可能です。
例えば、
「なぜか女性に対して横柄な態度になる方」
「主介護者がせっかちな息子さん」(男性同士の方が話が早い)
「男性好きの女性の利用者さん」
「乱暴な言葉を使う本人・家族」
「女性が苦手な利用者・家族」
‥など。
女性では難しい利用者・家族がおられるのも事実。
男性がいる居宅介護支援事業所は強みとなります。
ケアマネジャー収入は??私は共働きしてます。
介護業界は仕事の割に給料が少ないと言われていますよね。
そのため、介護業界で働くと決めたら、生涯共働きとなります。ですが、今では生涯共働きは約7割と、共働きの世帯平均年収は830万円と言われています。
そこで気になるケアマネジャー平均年収。ケアマネジャーの平均年収は400万円前後と言われています。
筆者はケアマネジャー歴10年で、地方暮らし。個人の年収は400万円に届かないくらい。
ちなみに妻は、介護保険のサービス事業所に務めており、夫婦合わせて750万円前後。そう考えると、割と悪くない生活をしていると自負しています(笑)
急な休みは、ケアマネジャーの方が対応しやすい
ケアマネジャーは、日々の業務は自分で予定を立てるので、自分の時間をコントロールしやすい。というメリットがあります。
デイサービスや訪問介護など、施設務めの方が時間に沿って仕事をこなしていくのにくらべ、ケアマネジャーは自分のスケジュールは自分で決めていくことに大きなメリットがあります。「子の授業参観の日は、仕事の予定を入れない。」なんて工夫もできるのは、ライフを充実させるために大きな魅力となります。
女性心を知らない男性ケアマネジャーは辛い
女性心を知らない男性ケアマネジャーは、敬遠されます。
男性は女性の共感し合う会話が苦手ですよね(笑)コレには、科学的に証明された理由があります。男性は課題解決のために会話をするのに対し、女性は共感を目的に会話を楽しんでいるからと言われています。
職場の仲間、利用者も女性とのコミュニケーションが多い業界なので、女心は勉強しておいて損はないです。
女性との会話に悩んだ筆者は、コレで勉強しました。
男だって、ケアマネジャーで人生を謳歌できる
迷いながらケアマネジャーへ転職し、10年がたった今でも、あのとき決心して良かった。と過去の自分を褒めてやりたいです(笑)
介護業界で働く男性は、将来の不安や女性が多い職場に戸惑いがあるかもしれません。ですが、ケアマネジャーの仕事はやりがいがあり、幸せな生活ができる収入を得ることができます(共働きにはなるけど)。
ケアマネジャーや介護業界でも、仕事とプライベートを両立・充実させましょう!
ではまた。